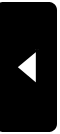2022年05月18日
東海道を新居関所から名古屋まで走ってみた。
こんにちは、大林です。
今日は、久しぶりに気持ちよく晴れ。仕事の合間に芝を刈りました。
さて、今日は少し前ですが、GWに東海道を新居関所から自分の足で走って熱田神宮まで行った話を。
なお、今年から5/3は独断で「東海道53次の日」に制定しました。

いま、「はっ?」って言いましたよね? たぶん「飛脚かっ!」って突っ込みましたよね?
まあ、普通言いますよね。 画像で見ると自分でも驚きます。
GWですし、普段やらないことをやってみたいな、というのと、私が高校で深く印象を受けた恩師(古典の先生)が4月に急逝されたこともあり、古きを訪ねる冒険みたいなことが無性にしたくなったのです。
「田舎の中学校で多少優秀でも、北高に行けば油断したらあっという間にビリだぞ。」と中学の先生に冗談交じりに脅され、無事浜松北高に入学し、1年2年と連続で担任してくださったのが、急逝されたノリオ先生。 めっちゃ怖いけれど、私にとってはとても印象深い恩師だった。
こっちは、田舎からドキドキしながら通っているのに、文法のカ変だのサ変だの、活用を暗記して指名されたら答えられないと立たされる。 これって、今はアカン指導なのかな。 当時は、この緊張感が嫌いではなかったけどなあ。
必死で覚えたので30年以上たった今でも、何だか覚えていないけど「かろ・かっ・く・い・い・けれ」とか、怖い顔と一緒に無駄に頭に浮かんでくるんだよなあ。
あと、徒然草だよね確か、「仁和寺にある法師」って話。 そのなかに「徒歩よりもうでけり」という言い回しがあり、何だかゴロが好きでよく覚えている。 「かちよりもうでけりの「けり」の品詞は何?、活用は何型だ?」なんて、授業中に当てられるとドキッとした記憶あり。
そんな断片的な思い出もチラッとあり、恩師の供養気分で「徒歩より詣でけり」をしてみた。 私にとっては石清水八幡宮ではなく熱田神宮だったけど。
「東海道」という響きは、静岡県民には当たり前すぎて、新鮮味がないのです。
県民にとってのお茶とみかんのような存在、あって当たり前みたいな感覚。 違う?でも、東海道線の色はオレンジと緑で常にそばにある感覚。
帰りは、JRか名鉄で戻ってくることが前提の鉄砲玉のような東海道ランを少し紹介。
まずは、江戸時代の旅人気分で、朝の6時前に新居関所を出発。

走ると行っても、旅であり、小さな冒険ですからね、やっぱりワクワクするわけですよ。

この旅籠「紀伊国屋」を出発した設定で、てなわけで。

旧東海道は、割と丁寧に看板があり、ある程度の予習は必要ですが、辿ることはさほど難しくは有りません。

潮見坂という言葉は国1だったり、国1バイパスだったりで頻繁に口にするのですが、旧道の潮見坂を走るのは初めて。本当に海の様子が見えるんだなとちょっと感動。

二川の街も何度も通過したことはありますが、線を辿ってここに辿り着く感覚が新鮮。
本当は行けるところまで行って足が動かなくなったら名鉄でもJRでも乗って帰ろうかと思っていたのですが、線をつなぎながら所々に残る昔の名残を探す感覚に、どハマリし、なんとか東海道の愛知県側を一気に制覇したくなりました。 行くぞ名古屋まで。

ワクワクしながら走っていると、写真を撮るのも面倒になり、いつの間にか豊川市の姫街道との合流地点到着。 ここから我がふるさと、細江町につながっているのだな。

御油の松並木という言葉は、昔から聞いたことがあったのですがここだったのか。 現存する立派な松並木。

赤塚宿に現存する、尾崎屋。 ガラッと板戸が開くと着物を着た人たちが出てきそうな風貌。

岡崎市にある、藤川宿の案内看板。 走っているので、当時の旅人の3倍速くらいで進行中のため、次から次へと宿場が現れます。 一里塚も数え切れないほど。 ここは自治体のやる気が見えていました。

ざっくりと、岡崎市中心部に昼までに着きたいなと思っていたところ、11時半に通過。 岡崎の街は、観光に力が入っていると見えて好感が持てます。くねくねに曲がった当時の東海道を看板で表記し、迷路感覚で楽しませてくれます。

私が、仕事柄すっかり気に入ってしまったのが、岡崎市の公園、籠田公園。
パッと見て楽しそうじゃないですか。 既製品の遊具をポンポンと並べた公園ではなく、使う人のことを考えて設計されている様子がビンビン伝わってきます。

2月に妻と、有松までドライブで来て、絞り染めの巾着袋を買って愛用しているのですが、なぜかまた来てしまいましたよ。それも自走で(笑)。

そして、ついに夕方。 東海道の愛知側の終点、宮宿(熱田神宮付近)の七里の渡しに到着。 ここから三重県の桑名に船で渡る(七里=28キロ)のが当時のルートでした。
GWの真っ只中ですが、バイパスの渋滞を後目に倍速で昔の旅人気分を味わいました。
点と点ではなく、連続した東海道めぐり・・・これはちょっと面白いですよ。
定年後の御夫婦が地図片手に歩く気持ちが分かってしまった49歳(苦笑)。
沿道の住宅も撮りそびれましたが、ヒントの宝石箱やー!、と言ったとか言わないとか。
趣味と仕事の両面で東海道に魅せられましたね。
今まで、軽く扱ってすいませんでした、東海道先輩!と謝りたい気分。
つくづく自分のことながら建物やまちづくりが好きなのだなと、10時間走りながら実感しました。
次回は、浜名湖の今切の渡しで対岸に渡った設定で舞阪宿から東に向かってスタートです。いつになりますかね。
大林勇設計事務所
今日は、久しぶりに気持ちよく晴れ。仕事の合間に芝を刈りました。
さて、今日は少し前ですが、GWに東海道を新居関所から自分の足で走って熱田神宮まで行った話を。
なお、今年から5/3は独断で「東海道53次の日」に制定しました。

いま、「はっ?」って言いましたよね? たぶん「飛脚かっ!」って突っ込みましたよね?
まあ、普通言いますよね。 画像で見ると自分でも驚きます。
GWですし、普段やらないことをやってみたいな、というのと、私が高校で深く印象を受けた恩師(古典の先生)が4月に急逝されたこともあり、古きを訪ねる冒険みたいなことが無性にしたくなったのです。
「田舎の中学校で多少優秀でも、北高に行けば油断したらあっという間にビリだぞ。」と中学の先生に冗談交じりに脅され、無事浜松北高に入学し、1年2年と連続で担任してくださったのが、急逝されたノリオ先生。 めっちゃ怖いけれど、私にとってはとても印象深い恩師だった。
こっちは、田舎からドキドキしながら通っているのに、文法のカ変だのサ変だの、活用を暗記して指名されたら答えられないと立たされる。 これって、今はアカン指導なのかな。 当時は、この緊張感が嫌いではなかったけどなあ。
必死で覚えたので30年以上たった今でも、何だか覚えていないけど「かろ・かっ・く・い・い・けれ」とか、怖い顔と一緒に無駄に頭に浮かんでくるんだよなあ。
あと、徒然草だよね確か、「仁和寺にある法師」って話。 そのなかに「徒歩よりもうでけり」という言い回しがあり、何だかゴロが好きでよく覚えている。 「かちよりもうでけりの「けり」の品詞は何?、活用は何型だ?」なんて、授業中に当てられるとドキッとした記憶あり。
そんな断片的な思い出もチラッとあり、恩師の供養気分で「徒歩より詣でけり」をしてみた。 私にとっては石清水八幡宮ではなく熱田神宮だったけど。
「東海道」という響きは、静岡県民には当たり前すぎて、新鮮味がないのです。
県民にとってのお茶とみかんのような存在、あって当たり前みたいな感覚。 違う?でも、東海道線の色はオレンジと緑で常にそばにある感覚。
帰りは、JRか名鉄で戻ってくることが前提の鉄砲玉のような東海道ランを少し紹介。
まずは、江戸時代の旅人気分で、朝の6時前に新居関所を出発。

走ると行っても、旅であり、小さな冒険ですからね、やっぱりワクワクするわけですよ。

この旅籠「紀伊国屋」を出発した設定で、てなわけで。

旧東海道は、割と丁寧に看板があり、ある程度の予習は必要ですが、辿ることはさほど難しくは有りません。

潮見坂という言葉は国1だったり、国1バイパスだったりで頻繁に口にするのですが、旧道の潮見坂を走るのは初めて。本当に海の様子が見えるんだなとちょっと感動。

二川の街も何度も通過したことはありますが、線を辿ってここに辿り着く感覚が新鮮。
本当は行けるところまで行って足が動かなくなったら名鉄でもJRでも乗って帰ろうかと思っていたのですが、線をつなぎながら所々に残る昔の名残を探す感覚に、どハマリし、なんとか東海道の愛知県側を一気に制覇したくなりました。 行くぞ名古屋まで。

ワクワクしながら走っていると、写真を撮るのも面倒になり、いつの間にか豊川市の姫街道との合流地点到着。 ここから我がふるさと、細江町につながっているのだな。

御油の松並木という言葉は、昔から聞いたことがあったのですがここだったのか。 現存する立派な松並木。

赤塚宿に現存する、尾崎屋。 ガラッと板戸が開くと着物を着た人たちが出てきそうな風貌。

岡崎市にある、藤川宿の案内看板。 走っているので、当時の旅人の3倍速くらいで進行中のため、次から次へと宿場が現れます。 一里塚も数え切れないほど。 ここは自治体のやる気が見えていました。

ざっくりと、岡崎市中心部に昼までに着きたいなと思っていたところ、11時半に通過。 岡崎の街は、観光に力が入っていると見えて好感が持てます。くねくねに曲がった当時の東海道を看板で表記し、迷路感覚で楽しませてくれます。

私が、仕事柄すっかり気に入ってしまったのが、岡崎市の公園、籠田公園。
パッと見て楽しそうじゃないですか。 既製品の遊具をポンポンと並べた公園ではなく、使う人のことを考えて設計されている様子がビンビン伝わってきます。

2月に妻と、有松までドライブで来て、絞り染めの巾着袋を買って愛用しているのですが、なぜかまた来てしまいましたよ。それも自走で(笑)。

そして、ついに夕方。 東海道の愛知側の終点、宮宿(熱田神宮付近)の七里の渡しに到着。 ここから三重県の桑名に船で渡る(七里=28キロ)のが当時のルートでした。
GWの真っ只中ですが、バイパスの渋滞を後目に倍速で昔の旅人気分を味わいました。
点と点ではなく、連続した東海道めぐり・・・これはちょっと面白いですよ。
定年後の御夫婦が地図片手に歩く気持ちが分かってしまった49歳(苦笑)。
沿道の住宅も撮りそびれましたが、ヒントの宝石箱やー!、と言ったとか言わないとか。
趣味と仕事の両面で東海道に魅せられましたね。
今まで、軽く扱ってすいませんでした、東海道先輩!と謝りたい気分。
つくづく自分のことながら建物やまちづくりが好きなのだなと、10時間走りながら実感しました。
次回は、浜名湖の今切の渡しで対岸に渡った設定で舞阪宿から東に向かってスタートです。いつになりますかね。
大林勇設計事務所